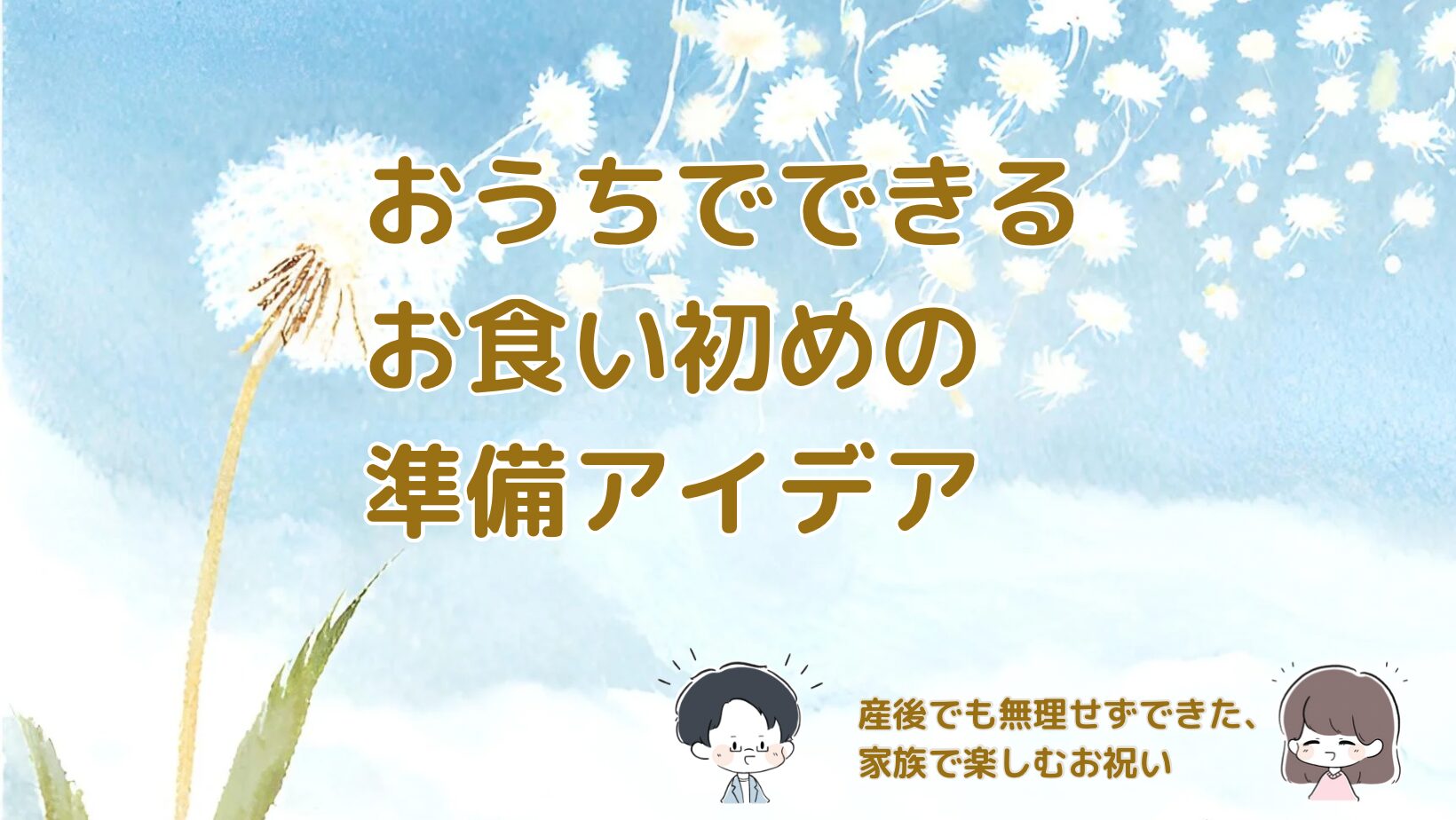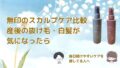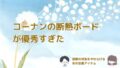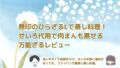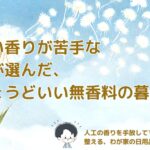どうも!“しとらす”と“ろーず”です。
七五三の準備をしていたら、娘の「お食い初め」の写真が出てきて、当時のことを思い出しました。
初めての行事って、何を準備していいのか分からず難しそうに思えるけれど、調べてやってみると意外と大丈夫なことも多いです。
今回は、産後の私でも無理なくお祝いできた“おうちお食い初め”の体験を紹介します。
お食い初めとは、生後100日頃に「これから一生食べ物に困りませんように」と願いを込めて行う儀式。
赤ちゃんの前にお祝い膳を並べて、食べるまねをさせる行事です。
地域によって内容はさまざまですが、わが家は家庭で手作りスタイルにしました。


自分で用意したけど、こんなしっかりとしたお食い初めができたよ!
スーパーで予約した鯛
鯛は近くのスーパーで「お食い初め用に焼いてください」とお願いしたら、お祝い風に立派に仕上げてくれました。
実は最初、それができることを知らなくて、近所のおばちゃんに「スーパーで焼いてもらえるよ」と教えてもらいました。
地域のスーパーによって対応が違うそうなので、気になる方は一度問い合わせてみるのがおすすめです。
鯛には“めでたい”の意味があり、お祝いにぴったり。
大きめだったので白いお皿にのせてシンプルに仕上げました。
赤飯は炊飯器で
赤飯は炊飯器で炊くだけ。手間はほとんどかかりません。
市販の赤飯の素を使って、簡単にお祝い気分を出せました。
赤い色には“魔除け”の意味があるそうで、昔からハレの日の定番です。
おかずは晩ごはんと兼用
はまぐりのお吸い物、タコときゅうりの酢の物、れんこんとこんにゃくの煮物。どれも晩ごはんと兼用で作りました。
お吸い物のはまぐりは“夫婦円満”、酢の物のタコは“多幸”。煮物は、れんこんが“先を見通す”、こんにゃくは“強い結びつき”など、縁起の良い意味が込められています。
すべてを完璧に揃えなくても、少し取り入れるだけで気持ちがこもるお祝いになります。
器はお宮参りでもらったもの
お宮参りのときに神社からいただいた器をそのまま使用しました。
当時は「お宮参りでお食い初めの器をもらえるなんて知らなかった」のですが、神社によってはお祝い膳やお守りなどの記念品をいただけることもあるそうです。
煮物の小皿は、お宮参り後に木曽路で食事をしたときにもらった器。
思い出の品を再利用できて、気持ちも温かくなりました。
費用は食材だけ
特別な道具は買わず、かかったのは食材費のみ。
スーパーや冷蔵庫にあるもので準備できたので、心にも体にも余裕がありました。
写真に残せば十分
鯛とお膳を並べて写真を撮るだけで、立派なお祝いの記録に。
産後の体には“がんばりすぎないお祝い”がちょうどよかったと思います。
無理せず続けられる形で、家族の記念日を残せるのがいちばん。

準備をがんばりすぎなくても、家族みんなで笑顔になれた日。
これからお食い初めを迎える方にも、そんな時間になりますように。
この記事が、あなたをやさしく後押しする”そよかぜ”になりますように。それでは!
関連記事
👉 おうちで記念写真!家族イベントにちょうどいいスマホ三脚
👉【体験談】スタジオアリスをネットではなく店頭予約した理由|着物・ドレス・神社も1日で完結!